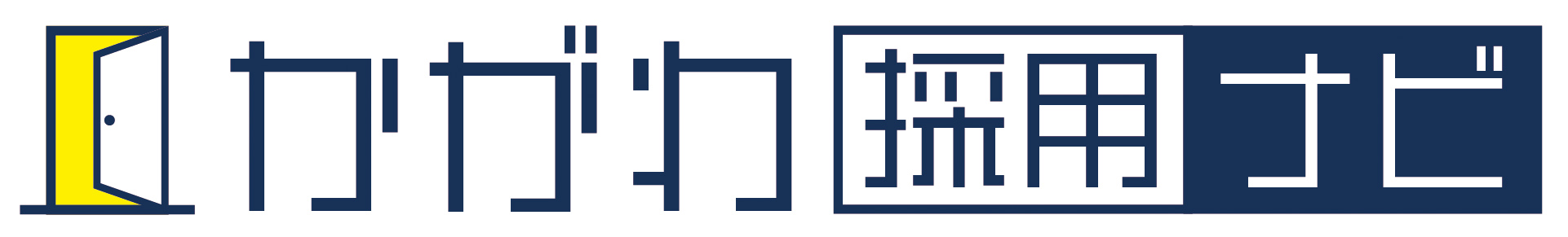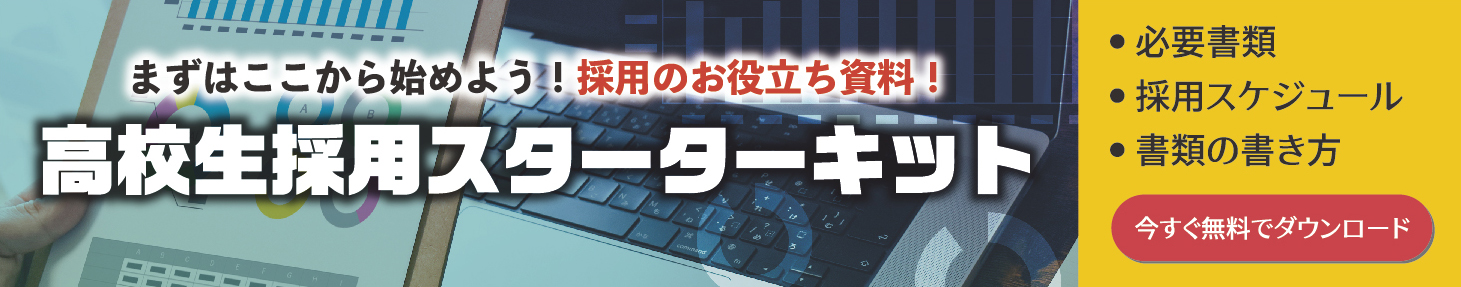「今の新入社員」を知る3つのキーワード
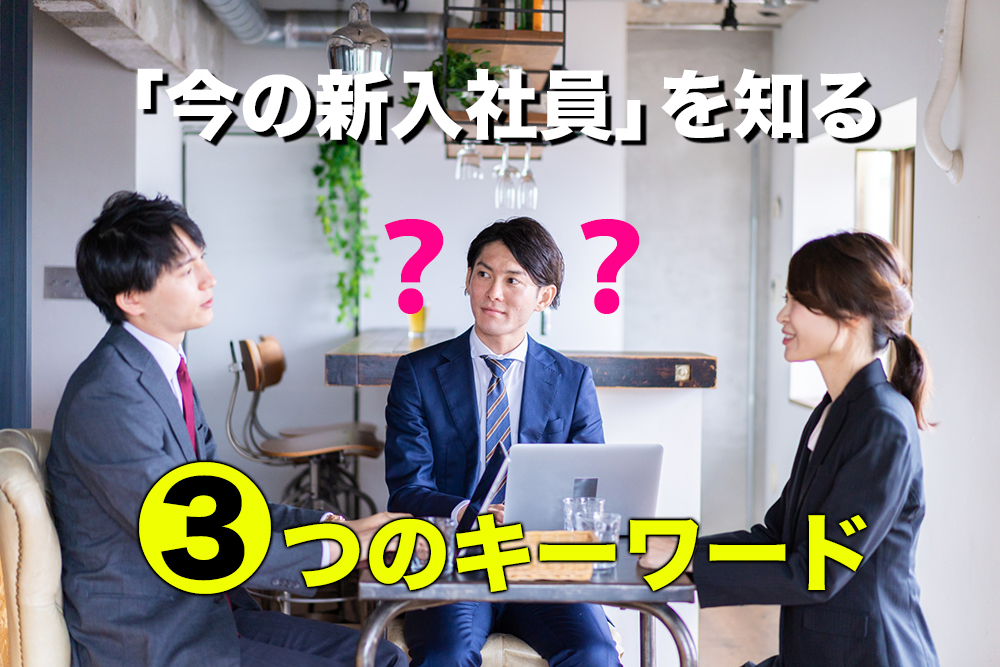
ゆとり世代ブームから数年が経過して、若い世代の感性もずいぶんと変化しています。
「うーん、本当に話が伝わっているんだろうか?」
「どう話かけたらいいのか戸惑うな…」
日本中の会社からそんな声が聞こえてきそうです。
「今の新入社員」をしっかりと理解したうえで新入社員研修なりOJTを進めないと、
思ってもみない方向…最悪の場合は早期退職という結果に陥ってしまう恐れもあります。
本コラムは、長年、大勢の新入社員を育ててきた研修のプロが実感した「今の新入社員」の本質をまとめた資料を参考にしています。「個」を大事にしましょうと言いつつ、「この世代の特徴はまとめて言うと…」などと矛盾した感じになってしまいますが、「今の新入社員」を理解するためのきっかけの一つにしてください。
新しい個性を持った世代は、なにも突発的に生まれてくるものではありません。
1)親と子の関係性「対等」
「今の新入社員」の親世代は、ざっくり言って30年ほど前に「新人類」と呼ばれた特異的なジェネレーションです。極端な受験戦争と、いまでは信じられないような管理された学生生活を強いられ、バブル時代を経験し、結果、「個性」を重要視する傾向が強いと言われています。古い上下関係を正しい価値観と考えず、「楽しむ」こと以外で他人と手を取り合う必要性を感じず、そしてなにより「面白くないから辞める」ことを躊躇しない…そう揶揄されていました。
そんな親に育てられた「今の新入社員」ですから、さらに「個」を大事にする感覚を持つのも当然と言えば当然です。もっとも身近な目上の存在である親に対しても、友だち的でフランクな立場が当たり前と考えています。親世代も(自分もそうだったために)それを否定せず、結果、(する、しないは別にして)自分というものをしっかりと主張する能力に長けています。
また、自分の中で明確な「善し悪し」「好き嫌い」「許す許さない」という基準を設け、いざとなればそれを行動に移すことも辞さない強い自我も持ち合わせています。
2)周囲との関係性「個と自分」
「今の新入社員」はゆとり教育のまっただ中で成長しました。間違ってはいけないのが、ゆとり教育=学力低下という誤解です。今の若い世代は、ゆとり教育だったぶん塾などでしっかり補なっており、決して学力的に劣っているとは言えません。特に特定のキーワードから何かの答えを見つけ出す「検索能力」は上世代は足元にも及ばないでしょう。
ただし、ゆとり教育の弊害として、「競争意識の低下」は否めません。運動会では1位を決めない徒競走をし、校内テストのランキングは発表しません。そういった「みんな仲良し横一列」な学生生活を送った末にいきなり受験戦争に放り込まれてしまい、「何が何だかよくわからなかった」と当時を回顧する方もいます。
詰め込み教育を脱却し、応用力を高め、個性をはぐくむ目的で始まったゆとり教育ですが、実際には他人との関わり(そのもっとも明確なものが競争)が希薄になり、「成功・失敗」に対する喜怒哀楽の感情を表す機会も減りました。「個性」は、周囲との関わりや、何かに熱中することのなかで「見つけていく」ものなのに、その機会を奪ってしまったと言えます。
そこにSNSというツールが登場したことで、「コミュニケーションは気心の知れた者どうしだけの空間でいい」という特徴を持つようになったのも当然のことでしょう。
3)社会との関係性「壁」

バブル後に生まれ、日本の(あらゆるものが)右肩下がりの現状を見て育った「今の新入社員」にとって、「努力は必ず報われる」という言葉は心に響きにくいでしょう。
社会のさまざまな(えらい人たちが考えた)立派な仕組みが予想に反して次々と失敗に終わり、それが声高らかに非難されている姿を見聞きしてきた世代です。また、情報過多といじめが無くならない環境で、「自分を守る」ことを幼い頃から求められてきたこともあり、他者との間にはっきりと『壁』を設けることを意識づけられてきました。
そんな彼らに、問答無用で「夢を見ろ!」「希望を持て!」というのは、いささま無責任ではないでしょうか?「好きなときに、好きな人とだけコミュニケーションをとる」のがあたりまえの世代に、他人である上司・先輩が意思を伝えるのは難しいでしょう。
4)ではどうすれば?
日々、リアルにこういった世代の方たちと会っていて感じるのは、決して彼らが他者とのコミュニケーションを嫌っているわけではない、ということです社会不安・経済不安・将来への不安と、ネットからも不安を押し付けられ気味の「今の新入社員」には、なんらかのジレンマを抱えている人が多いようです。
もちろん個人によって差異は大きいでしょうし、パターンを決めてそこに当てはめようとすること自体、彼ら世代には承服しがたい決めつけ行為と捉えられるでしょう。
なので新入社員を迎え入れる側としてできること、やらなければならないことは、とにかく「話を聞く」ことに限られるのではないでしょうか? 相手はひとりの「個」です。ちゃんと認めて、ちゃんと話を聞いて、そのうえで「型にはまった対応で済ませようとしない」。そこから、もっと戦力になる社員へと成長させる教育が始められるのではないでしょうか?

5)まとめ
いかがだったでしょうか? 今回は定型の解決策のない「個」についてまとめました。あくまで平均的な特徴づけとなりますが、偏った基準をもって対応してしまい、思いも寄らぬ誤解や齟齬が生じてしまう危険性を避けるためにも、理解しておくことが必要です。
なお、かがわ採用ナビでは、香川県内の企業の採用サポートを実施しています。
・どんなふうに採用活動をすればよいか分からない
・採用戦略をしっかり考えたい
など、些細なお悩みでも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。