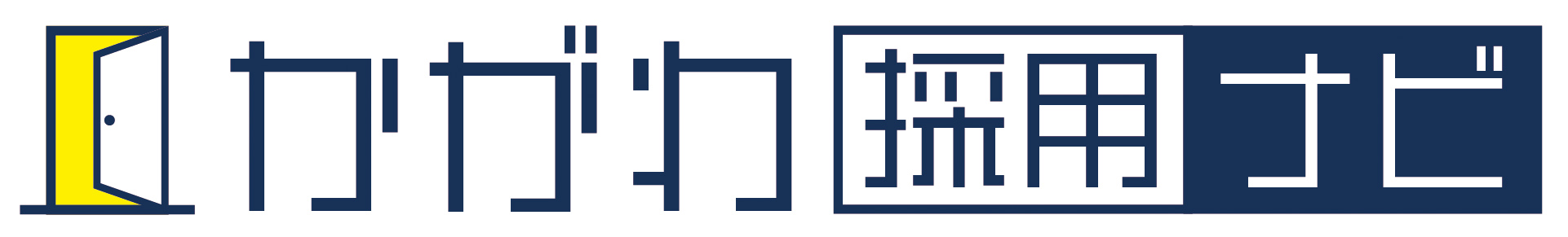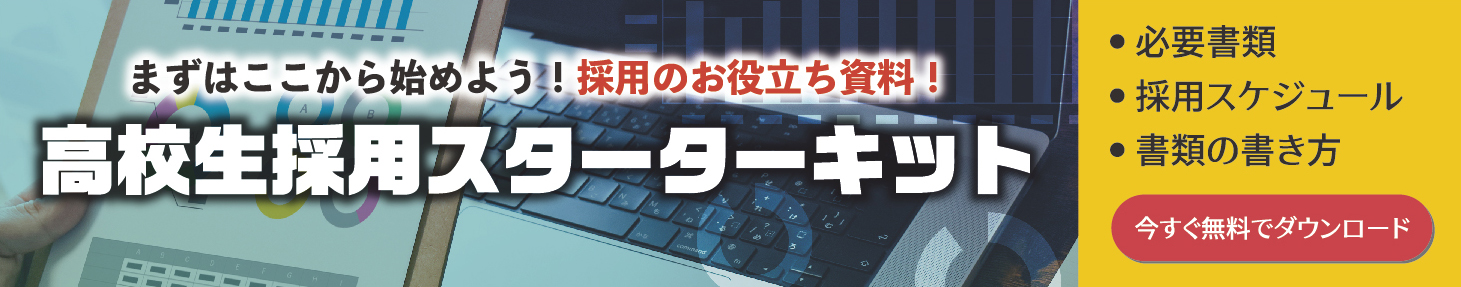早期離職の原因徹底解説!早期離職を防ぐ方法!

近年、若者の早期離職率が増加傾向にあります。せっかく採用に力をいれていたのに、早期でやめられてしまうというのは企業にとっても負担が大きいです。
今回は早期離職の原因と対策についてお話していきます。早期離職を防いで長く働いて欲しい採用担当者の方は是非ご確認ください
①早期離職とは
早期離職とは早期離職とは、一般的に入社してから3年以内に離職した人の割合を指す。毎年厚生労働省が発表している「学歴別卒業後3年以内離職率の推移」によると大卒で3年以内に離職する割合が3割を超えており、企業としても採用・育成コストが増加してしまうことなどでの影響を受けている。
②早期離職の現状
離職率の現状は?
現在、若手人材はどのくらいの割合で離職しているのか。 厚生労働省の調査(※)によれば、就職後3年以内の離職率は、大卒で「32.8%」、高卒で「39.5%」、短大等卒で「43.0%」、中学卒で「59.8%」となりました(平成29年3月卒業者)
③早期離職の原因
退職のきっかけ
1位 「やりがいの欠如」
2位 「給与」「拘束時間」
3位 「成長感の低下」
4位 「企業の将来性」
5位 「家庭の事情」
早期離職の理由として上位にあげられた5つのものについて、それぞれの要因が早期離職へつながる原因や、具体的な対応策を詳しく解説していく
- 賃金や給与への不満
- 業務内容へのリアリティショック
- 企業の将来性への不安視
- 人間関係やカルチャーへの違和感
- ワークライフバランスなど労働環境への不満
1・賃金や給与への不満
「賃金や給与への不満」を早期離職の原因として挙げた人は41%で、年齢層を問わず特に多い結果となっている。
内閣府が行った調査によると、16歳から29歳までの男女が仕事をする目的で最も多いのが、「収入を得る為」で約85%を占める。2位の「仕事を通して達成感や生きがいを得る為」が約15%なので、収入を目的とする人が突出して多いことが分かる。
つまり、多くの若者にとって賃金や給与が、仕事を選ぶ上で最も重要な要素だということとなる。
仕事をする目的についてみると、「収入を得る為」と回答したものが84.6%と突出して多く、「仕事を通して達成感や生きがいを得る為」と回答したものが15.8%、「自分の能力を発揮するため」と回答したものが15.7%、「働くのが当たり前だから」と回答したものが14.8%、「人の役にたつため」と回答したものが13.6%であった。
収入さえ多ければ、労働時間が多少長く感じてもモチベーションを維持できるが、収入が低ければ社員のモチベーションも低下するため、離職率への影響が大きくなる。多くの日本の企業では、年功序列や終身雇用を前提としてきたため、若年層の賃金は低く、年齢層が高くなるにつれて賃金が上昇する傾向にある。しかし、年功序列や終身雇用のシステムが崩れ始めている現在では、年齢が原因で賃金が低いことに納得できないという人も少なくはない。こうした賃金への違和感が、離職率野高さにつながっている。
賃金を理由とする早期退職を防ぐためには、社員の評価制度を見直し、能力や働きぶりに見合う賃金を提供することが大切となる。適切な対価を与えられることにより、社員のエンゲージメントが高まる。また、社員一人一人の負担を減らすのにも採用強化による人材不足の解消も欠かせない。
2・業務内容へのリアリティショック
業務内容へ「リアリティショック」を感じて、働きがい・やりがいがなくなったことは、離職理由の41%を占めている。リアリティショックとは理想と現実の違いに衝撃を受けること。
具体的には実際の職場環境や仕事内容のイメージが、入社前にイメージしていた物と違う場合を指す。例えば、入社前の説明では実力主義でやりがいのある仕事だと伝えられていたのに、実際入社すると単調な仕事しか与えられない場合などの事。
このようなことがあると、社員が働く意味・やりがいを感じられなくなるため、より理想的な職場を求めて早期離職へと繋がる。
リアリティショックとは、企業側による過度な採用ブランディングや情報提供の不足などが原因で起こる。自薦のイメージと実態とのギャップがあるまま採用候補者が入社し、ミスマッチが生じて離職へとつながる。
リアリティショックを防ぐためには、自社の業務内容を採用候補者によく理解してもらうことが重要。会社説明時の説明を具体化するだけではなく、可能であれば体験入社や職場見学の機会を設けて、実際の職場環境や業務内容等を理解してもらうことが重要。
3・企業の将来性への不安
「企業の将来性への不安」を理由として、早期退職した人は36%となった。近年ではひとつの会社に定年まで働き続けるという、終身雇用の概念はなくなりつつある。しかし、候補者にとっては安定した生活や、将来へのキャリア形成ができる環境は重要。
そのため、企業の将来性に不安があると、社員の離職へつながります。特に、ベンチャー企業のような業績が安定していない企業では、「ここで働き続けても大丈夫なのか」という社員への不安もより大きくなります。
内閣府の調査によると、職場選択の際に重要視する要素として、9割近くの人が「安定して長く続けられるところ」と挙げている。つまり、終身雇用が一般的ではなくっても、採用候補者は安定感を重視するということ。
仕事を選択する際に重要と考える観点について、「安定して長く続けられること」、及び「収入が多いこと」に、「とても重要」または「まあ重要」と回答した者は、ともに88.7%で最も多かった。次いで多かった項目は、「自分のやりたいことができること」の88.5%、「福利厚生が充実していること」の85.2%、「自由な時間が多いこと」の82.2%であった。一方「実力主義で偉くなれること」と「特別指示されずに、自分の責任で決められること」を「とても重要」、または「まあ重要」と回答した者は、それぞれ51.6%、55.8%と比較的少なかった。平成23年度の調査時においても、「安定していて長く続けられる」、「収入が多い」、「自分の好きなことができる」といった類似の項目に「とても大切」、「まあ、大切」と回答した者は多かった。
企業の将来性への不安を理由とする早期離職を防ぐためには、社員の不安を解消する努力が求められる。企業が上場していない場合、決算結果の開示義務はない。自社の価値や経営の見通しについて、不安材料も含めて可能な範囲で社員と共有することにより、社員の信頼を得やすくなる。
4.人間関係やカルチャーへの違和感
「人間関係や企業カルチャーへの違和感」が早期離職へつながったと答えた人は35%。人間関係は、社員の離職率を大きく左右する。例えばセクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントがあったり、先輩や同僚との関係が悪くなったりすると、エンゲージメントやモチベーションに悪影響を与える。
5・ワークライフバランスなど労働環境への不満
企業の労働環境への不満が、早期離職につながったと答えた人は26%。近年では、多くの採用候補者が「ワークライフバランス」を重視している。ワークライフバランスとは仕事と生活のバランスをさす。内閣府の調査にもよると仕事よりも家庭を優先するという声が多かった。
残業時間や休日出勤が多かったりすると、休暇で自由な時間を過ごす機会が減る。ワークライフバランスが原因の早期離職を防ぐためには、残業時間や休日出勤を減らすことが重要・また、有給休暇を積極的に取得できるようにして社員が働きやすい環境を整備する。社員がリフレッシュしやすい環境を整えれば、パフォーマンスも向上していく。
④早期離職の予防策
・採用段階での早期離職対策
採用段階でのプロセスを改善することで、早期離職を大きく改善することができる可能性がある。採用のミスマッチやリアリティショックは、いずれも採用候補者が理想とする職場環境や業務内容が、現実のものと大きく異なることが原因。そのため、下記のような手法を導入して、早期離職を防いでいく。
・リファレンスチェック
・構造化面接
・インターンシップ
「リファレンスチェック」とは、採用候補者が以前勤めていた職場の担当者に対し、スキルや働きぶり等をお紹介すること。リファレンスチェックは採用候補者の同意が必要ではあるが、採用試験や面接だけでは図ることができない、採用候補者の本質的な適性を調べることができる。
「構造化面接」は、選考基準や質問事項などをあらかじめ決めておき、事前に定めた手順通りに面接を行う手法である。従来の面接手法で問題とされていた、採用担当者ごと判断基準のばらつきを抑えて、公平に検討できることが特徴。適切な設計をおしておくことで、採用候補者の能力や適性を客観的に見極めることができる。
「インターンシップ」は、採用候補者が入社前に企業へ訪問したり、実務を体験したりする制度で、就業体験とも呼ばれている。採用候補者が企業の職場環境や業務内容などを体験できるため、イメージとのギャップやミスマッチを減らせることが魅力的。ただし、印象づくりや採用候補者の囲い込みを過剰に行うと、逆にミスマッチの原因となるため注意が必要。
⑤まとめ
採用後から定着までの早期離職対策
人材を採用してから企業に定着するまでの間も、早期離職が発生しやすいため、採用候補者を丁寧にケアすることが重要である。この期間では、リアリティショックやカルチャーフィットなどの点で、特に問題が発生しやすい傾向がある。そのため、「オンボーディング」という施策に注力して、社員の想起離職を防いでいく。
オンボーディングとは、新入社員ができるだけ早いタイミングで活躍できるように、企業への定着や人材育成を行うこと。オンボードとは「乗船」を意味し、新入社員が組織に定着しやすくなる効果がある。一般的な新人研修は、業務に最低限必要な内容にとどまるが、オンボーディングは配属後の実務でも役立つ人材育成ができることも魅力。
適切なオンボーディングを行えば、新入社員がパフォーマンスを発揮して、実務で活躍できるようになるまでの期間がみじかくなる。自身が活躍できる環境を期待してs入社した新入社員は、退屈な業務ばかりを任されているとリアリティーショックが生じ、離職へつながることがある。オンボーディングの導入により、新入社員のエンゲージメントが高まる。
上記で説明したことを実践し、早期離職を防いでいくことが望ましい。