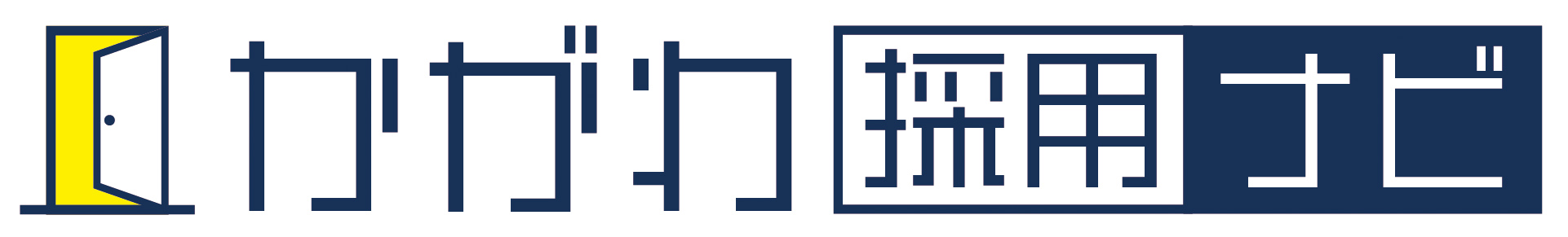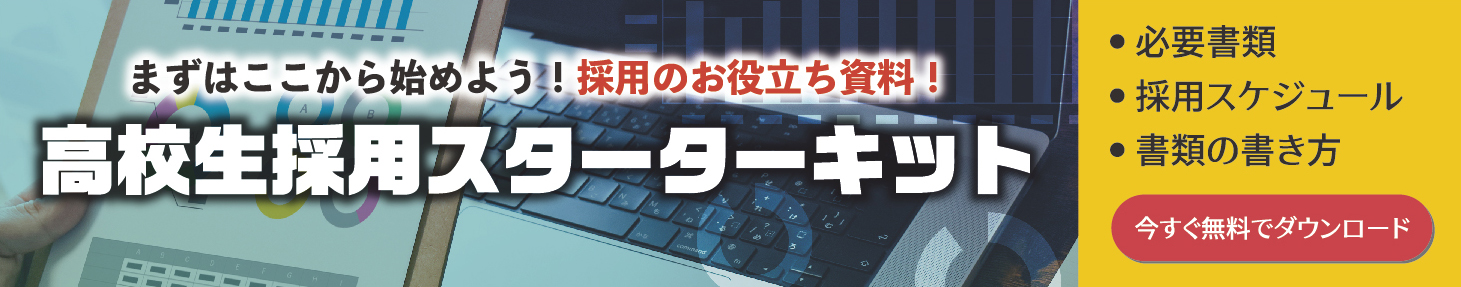香川県の今後の気になる採用動向

人口が減少傾向にある昨今。採用活動も年々厳しくなっているのが現状です。
今回は今後の採用マーケットの動向について解説していきます。今回取り上げた内容を元に今後の採用活動にお役立て下さい。
今後の採用マーケット
近年の新卒採用はマーケットが非常に流動的です。大手企業を中心に、各社がインターンシップといった早期での施策に力を入れていくと思いますので、さらに不安感が増しています。
今後企業はどこに採用の焦点を絞っていけばいいのでしょうか。
確かに、セミナー開催やエントリーなどで採用の母集団を作り、そこから選考を行うというプロセスが現在では最も浸透しているアプローチです。しかし、戦い方はひとつではありません。
このアプローチの場合、最初の接点は「来てもらうのを待つ」ことなので、人を集める力=知名度が重要な要因になることは否めません。
そこで、 知名度のない企業は「来てもらうのを待つ」戦略だけではなく、併用して「採りにいく」戦略を持つべき だと思います。
「採りにいく」戦略では、 最初の接点をどのように作るかが重要 です。
例えば、「採用実績がある」という事実をもとに行えば、その場において知名度の低さは大きな障害ではなくなるでしょう。
オーソドックスな手法だと、採用実績のある大学のゼミや課外活動の団体(体育会やサークル、ボランティア)にこちらから連絡。そして、OB・OGと共に企業紹介に行き、そこから個人単位で関係構築を始めるなどが考えられます。
そのようなきっかけから、数年間学生を採用することができれば、チャネルはその実績によって強化され、そのゼミや団体とはお互い信頼関係がある、という状態が構築できます。
このように、 どの学生をターゲットにして、その後どのように関係性を維持していくか考えることを、チャネルの設定といいます。
中小企業で強い採用を実現している企業は、独自のチャネルを構築しています。
例えば、ある企業では採用数の3割程度をアルバイトから登用しています。新卒採用の仕組みとして優秀なアルバイトには早いうちから働きかけ、意図的に会社のビジョンや将来構想を話して関係構築に努めています。
またある企業では、地元の学校から不景気の時にも毎年定期的に採用を続けたことで信頼を獲得し、今では推薦という形で毎年その学校で成績優秀な学生を獲得できるようになっています。
チャネルを複数持つことで、採用活動のリスクは分散され安定します。
すぐに結果がでない場合もありますが、場合によっては知名度よりも確実な武器になるでしょう。マーケットの変動が大きいからこそ、各企業にとって行動を起こすきっかけの年になるのではないでしょうか。
また、対学生においては、 改めて地方の企業ならではの良さをきちんと打ち出す必要 もあると思います。
時代的にも地方で働くことは決してネガティブな要素ではないからです。
最近では衣料品店ユニクロを運営するファーストリテイリングが、転勤がなく時短勤務が可能な地域正社員の選考会を北海道で開催して話題になりました。
ファーストリテイリングは知名度の高い企業ですので、このケースが該当するかわかりませんが、私は「地方で働く事」を前面に打ち出す場合に重要なことは、ただ「転勤がない」というような単語を伝えるのではなく、そこで起こる仕事を中心とした生活全体の様子を、ストーリーとして伝えることだと思います。
地方には、都心では味わえない豊かなストーリーが溢れています。
学生がそのストーリーに共感する可能性は決して低くありません。むしろ地方にある事で、ポジティブなストーリーをつくることも可能だと思います。
香川県の人手不足の現状
人手不足の悪影響が出ていると回答した県内企業の割合は 41.5%。少子高齢化で長期的に働き手が減少していくなか、緩やかな景気回復の影響も加わり、 企業の人手不足感が高まっている。香川県の有効求人倍率(除く新規学卒者、含むパート タイム)は、平成 24 年 12 月の 1.04 倍からその後上昇傾向となり、平成 26 年 7 月には 1.44 倍となっています。その後はやや低下したものの、平成 26 年 11 月現在、1.27 倍と 1.2 倍台 を維持して推移しています。有効求人倍率を雇用形態別にみると、正社員の有効求人倍率は 1 倍を割り込んで推移しているものの、これも改善傾向にあり、平成 26 年 11 月現在、0.92 倍となっています。有効求人倍率は、景気動向と一致して動く経済指標であることからすると、香川県内の景気は概ね改善傾向にあると言えます。 しかし、香川県の有効求人倍率には、職業別にみると大きな偏りがあります。 例えば、平成 26 年 11 月の状況をみると、「建設・採掘の職業」の有効求人倍率 4.06 倍に 対して「事務的職業」は 0.41 倍と、3.65 ポイントもの大きな差があります。細区分で特に倍 率の高い(人手が足りない)ものをみると、「建設・採掘の職業」のうち「建設躯体工事の 職業」が 11.76 倍、「土木の職業」が 4.78 倍、「建設の職業」が 4.59 倍、「専門的・技術的 職業」のうち「医師、薬剤師等」が 6.18 倍、「建築土木技術者」が 4.28 倍とその倍率の高 さが目立ってきていることが分かります。
こういったデータを知っておくことも今後の採用活動には必須となっていきます。
コロナ禍での採用動向
コロナウイルス収束後を見越して「人的投資」を積極化する企業は多くなっております。
初めにお伝えしておきたいのは、コロナ禍以前から構造的な人材不足や、サービス経済化・DX(デジタルトランスフォーメーション)化の進展により、企業の経営戦略や採用戦略に質的転換が起きていた、ということです。足元で採用活動を一時休止する企業はありますが、この質的変化の流れは今後も続くと考えられます。
そして、業界変容、戦略の複線化を受け、「業界一括りでは語れない」というのも今の転職市場動向の特徴となっています。
例えば、観光業や小売業、飲食業などコロナ禍の影響を大きく受けている業界がある一方で、医療や物流・運輸、EC関連、通信関連など、これまで以上に採用が活発化している業種や企業が存在します。さらには、「コロナ禍の影響が大きい」と言われる業界においても、事業への影響や経営戦略、そしてそれに呼応した採用戦略は企業によって異なることから、採用を継続している所もあります。
加えて、同じ企業内であっても、既存事業を中心とした守りの人事戦略と、市場創造を見越した攻めの採用戦略が並存するケースもあります。例えば小売業において、店長の募集はいったん止めるものの、ECサイトの売り上げは好調なのでカスタマーサポートやデジタルマーケティング担当の採用にはアクセルを踏んでいる、というところも散見されます。
とはいえ、足元で新たな中途採用に踏み切ることに不安を覚える企業も多いことでしょう。
ただ今後も、コロナウイルスに適応した新たな生活様式や経済活動が加速してゆくでしょう。そのときに機動的な事業創造や拡大のための人的資本が維持できているかどうかが問われています。
リーマンショック時、採用を停止した企業や雇用を維持できなかった企業は、その後の業績回復に時間がかかりました。短期的な視点ではなく、中長期的な視野で競争力を維持・向上するための採用戦略を考えることが重要なのです。「IT通信」「コンサルティング」「インターネット」の採用ニーズは活況です。続いて、業界別の転職市場動向についても触れておきたいと思います。今回は、「IT通信」「コンサルティング」「インターネット」の3業界について、解説します。
これらの業界は、いずれも企業や事業領域ごとに濃淡はあるものの、全体的には採用ニーズは活発です。
「IT通信」業界においては、新型コロナウイルス禍で通信キャリア系やネットワーク系に強みがある企業の求人が活況。在宅勤務環境への移行の流れを受けて通信のニーズが高まっていることに加え、5Gの案件も増えています。働き方改革の流れを受けたセキュリティ関連の事業・サービスや、物流システム関連を扱う企業も採用も活発です。
即戦力の採用ニーズは以前に引き続き旺盛で、特にデータサイエンティスト、IT(DX)コンサルタント、クラウド知見のあるインフラエンジニア、セキュリティエンジニア、システム監査などのニーズが高まっています。一方で、未経験者育成ができる状況であるところは限られており、昨年までの第二新卒・未経験採用の動きは鈍化しています。
「コンサルティング」業界は、採用に力を入れている部門と落ち着いている部門に分かれています。新型コロナウイルス禍の影響もありニーズが高い傾向にあるのは、通信・リスク管理・業務改善関連の求人。通信ではもともと5G関連の案件があったところに、テレワーク対応に伴うネットワークの再構築などの案件が発生しています。リスク管理では、会計やガバナンス強化だけではなく、サイバーセキュリティ関連のニーズが増加。業務改善では、省人化・生産性向上のためのIT導入やアウトソーシングなどの動きも出ています。なお、これまでは第二新卒採用が活発でしたが、現在はシニアコンサルタントレベル以上のニーズが高まっています。即戦力のコンサルタントだけではなく、コンサルタント経験がなくても、必要とされる業界の知見があり業務改善経験があれば採用したいという企業が多いのが特徴的です。
「インターネット業界」採用ニーズは、領域ごとに濃淡はあるものの、全体としては5月から緩やかな回復傾向にあります。業務支援のSaaS系サービスについては、顧客のDX推進に伴い事業も好調、採用も活発で、営業企画や営業・開発ポジションまで幅広く求人があります。外出自粛の影響でユーザー数が増えているゲームやライブ配信事業についても、人手不足が顕著になっています。この状況下で企業に問われているのは、「なぜ今、採用するのか?」という目的・背景をしっかりと求職者に伝える姿勢です。
人が協働体に参加する際の魅力要因は、「目標への共感」「活動内容への魅力」「構成員への魅力」「特権への魅力」の4つに分類され、この4つのうちどれかに魅力を感じると参加したくなると言われています。コロナ禍においては特に、「目標への共感」が重要。事業戦略と紐づく投資領域なのか?事業リスクを軽減する守りの領域なのか?明確に伝えることができなければ採用が難しくなっていくでしょう。
そして、Web面接に対応できる企業と、そうでない企業では、採用に大きな差がつくと予想されます。求職者のライフフィット志向は、採用プロセスにおいても顕在化しており、「時間や場所にとらわれない転職活動がしたい」「Web面接を実施している企業と優先的に出会いたい」という意向はさらに高まっています。
特にIT分野においてWeb面接に対応していない企業は、「Web面接もしていないのにDXだなんて…」などと思われてしまう可能性が高く、事業戦略にすら猜疑心を持たれてしまう恐れもあります。コロナ禍のみならず、これからの採用においては、Why(なぜ採用するのか)とHow(どういう方法で選考を行うのか)がますます問われるようになるでしょう。
まとめ
Z世代の特徴を踏まえ、採用戦略の策定にご活用いただける内容となっていますので、是非自社の新卒採用にお役立て頂けると幸いです。
また今回の内容以外の事で困りごとがあれば、是非お問い合わせください。
皆さんからのお声をお待ちしております。宜しくお願い致します。