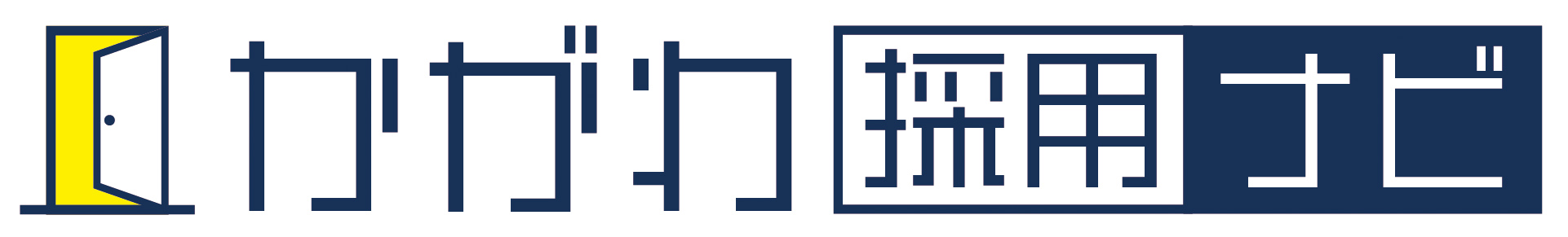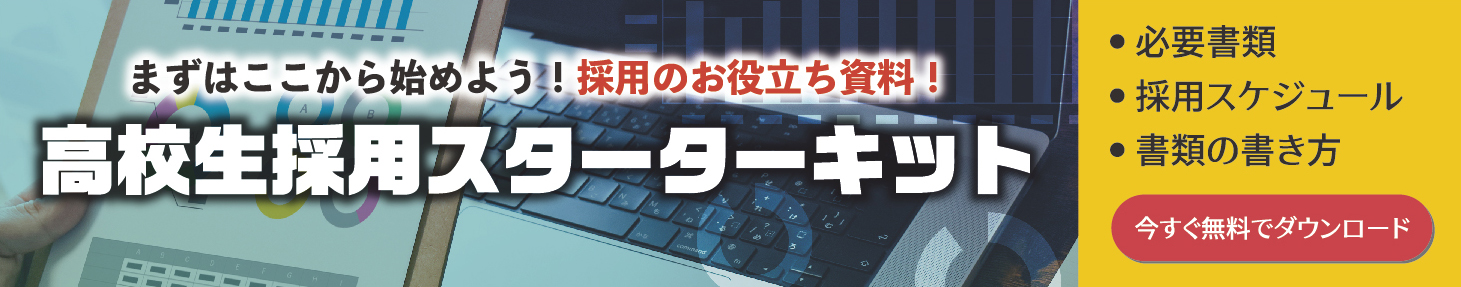企業・学生必見!インターンシップ活用術!

近年、高卒・大卒採用に力を入れている企業が増えています。
そんな中、企業側も学生側もインターンシップに力を入れていっているのが現状です。
インターンシップを活用して企業側も、学生側もリアリティショックがないようにしていきましょう。是非ご確認して頂き、今後の参考にしてください。
インターンシップとは
インターンシップとは、学生が実際に仕事を体験する制度のことで、“就業体験”とも言われております。
欧米では多くの企業が採用しており、学生がインターンシップ制度を利用することがもはや主流となっております。日本でも2000年代より徐々に普及し始めています。学生にとって社会に踏み出す前の貴重な経験の場となり、また企業によっては採用活動の一つとして実施していることもあります。
インターンシップでは収入が得られることもあるので、アルバイトと混同してしまう人もいるようです。インターンシップとアルバイトの主な違いはその目的にあります。つまり、インターンシップの目的は仕事の内容や自身の適性を理解することにあるが、アルバイトの目的は労働と時間の対価として給料をもらうことにあります。インターンシップとアルバイトは別物だということを理解したうえで、企業での就業体験に取り組むことが大切です。
高卒採用と大卒採用におけるインターンシップの違い
・活動スケジュールが違う
私は高校生の時はすでに進学を決めていたのであまり就職のことについて深く考えていなかったのですが、当時、就職を決めた同級生は高校3年の一学期の頃に履歴書の書き方や面接対策をして、夏休みの間に企業見学をして内定をもらっていたようでした。
短い期間の中で履歴書を作成したり企業に行ったりして、とても大変そうだったことを覚えています。そして今、COURSEのお仕事で企業や学校と関わってきてから高校生は厳しいスケジュールの中で、就職活動を行っているのを知りました。
また、一般的な企業の高卒採用活動においては、学校の先生から生徒を紹介してもらうという「学校斡旋」になります。そのため、7月に求人が解禁されると、まず企業は学校に足を運び、進路指導担当の教師に求人票を渡しに行く、もしくは郵送します。そして取りまとめた求人票を教師が生徒に紹介し、その中から生徒が興味のある会社があれば、面接前職場見学をします。高校3年生の2学期にあたる9月から一次の応募の学校推薦が開始するので、応募したい会社があれば生徒が教師にその意思を伝え、教師から企業に応募書類を送り、選考に進むというのが一般的な流れとなっております。
・高卒採用ならではのルール、大卒採用との違いは?
大卒採用の場合、大学生のほうから企業にアプローチするのが普通なので、企業側も大学生が見るであろう、大手求人サイトに自社のプロモーションを掲載したり、大学生が集まる採用イベントに出たりする事が、採用の最初の流れになります。しかし、高卒採用の場合、企業がまずやることは各高校の進路指導の教師に連絡をとることです。採用の鍵は、先生からどれだけ生徒を紹介してもらえるかにかかっています。
もう一つ大卒採用との大きな違いとしては、高卒採用では多くの都道府県で「1人1社制度」というルールがあります。職場見学は2~3社訪問する生徒が多いですが、選考を開始してからは1人1社しか応募できないことになっています。採用通知後の辞退や検討ということはまずなく、そのまま承諾して4月に入社するのが基本です。70年間ほど続いている伝統的な流れですが、この制度もあってミスマッチにつながりやすいという面もあります。
高卒採用でのインターンシップのポイント
・高卒採用は、企業側の受け入れ態勢が今後の課題
このように高卒採用には、大卒採用とは違った独自のルールがあります。一番のデメリットである離職率の高さを払拭し、入社後のミスマッチを防ぐために、会社のことや仕事のことを分かりやすく伝えること、高校生と接点がとれる職場見学や面接で相互理解を深めること、そして企業側が教育体制を整えることなども課題になりそうです。
大卒採用でのインターンシップのポイント
①参加する目的を明確にしておきましょう!
受け身にならないように、そしてのちの就職活動にも役立てられるように、自分なりの目標を設定しておくことが重要です。例えば、「参加してどういう風に成長したいか」「どのようなことを学びたいか、知りたいか」など、参加する目的を明確にして、参加する心構えをしっかりしておきましょう。
②会社や業界について詳しく調べておきましょう!
参加する企業や業界のことを事前に把握しておくことで、当日のプログラムにすんなりと入っていくことができます。また、事前に企業や業界の知識を得ておくことで、インターンシップ先の社員の人とより深い話ができるようになるなど、周りと一歩差をつけることができるかもしれません。さらに、関連するニュースにも目を通しておくとより良いでしょう。
③プログラムの内容と会場をしっかり把握しておきましょう!
参加するインターンシップの内容や目的を改めて確認し、当日はどう行動していきたいかイメージしておきましょう。そうすることで、当日落ち着いて自分自身の力を発揮することができ、得られるものも多く、インターンシップを有意義な経験にすることができます。
また、遅刻しないように会場名、会場の最寄駅、最寄駅からの道順、利用する交通機関など念入りに調べておくと当日焦らなくて良いでしょう。
④自己紹介ができるようにしておきましょう!
インターンシップでは自己紹介を求められる場面があるかもしれません。急に振られても戸惑わなくて良いように、ある程度話す内容を準備しておくと良いでしょう。今後、就職活動をする時の自己PRの練習にもなります。
⑤企業への質問を考えておきましょう!
企業研究や業界研究をしていくうちに、気になることやわからないことが出てくると思います。事前にノートにメモして、いつでも質問できるようにしておきましょう。質問の内容によっては、きちんと企業研究ができている学生だなと、好印象を持ってもらえる可能性もあります。
⑥最低限のマナーも確認しておきましょう!
無理に慣れない敬語を使って、固くなるよりは、学生らしく明るく元気に取り組めば、印象が悪くなることはないと思います。しかし最低限のマナーは身につけておくと良いでしょう。元気な挨拶、一般的なマナー、インターンシップの場を設けてくれている企業への感謝の気持ちなどは押さえておくべきポイントです。
まとめ
高校生、大学生それぞれの特徴、利点の違いが面白かったです。また就活スケジュールや使用する履歴書も違うなど、衝撃的なことがかなり多かったです。
特に面接が一回のみというのが効率的なシステムだと思いました。
しかし今の高校生の就活方法は、学校と企業側のサポートが行き届いていて良いやり方だと思うのですが、やはり大学生などに比べて就活の自由度は若干低めだと感じました。
今後、ルールがより良く変わったら高校生たちも今より満足した就活を進められるのではないかなと思いました。
是非このコラムを今後の採用活動にご活用下さい。
また、このほかにも採用関係などで些細なお困りごと等ございましたらお気軽にご相談ください。一緒にいい採用活動にして行きましょう。
ここまでご覧いただき、誠に有難うございました。
今後ともこちらの採用コラムをよろしくお願い致します。