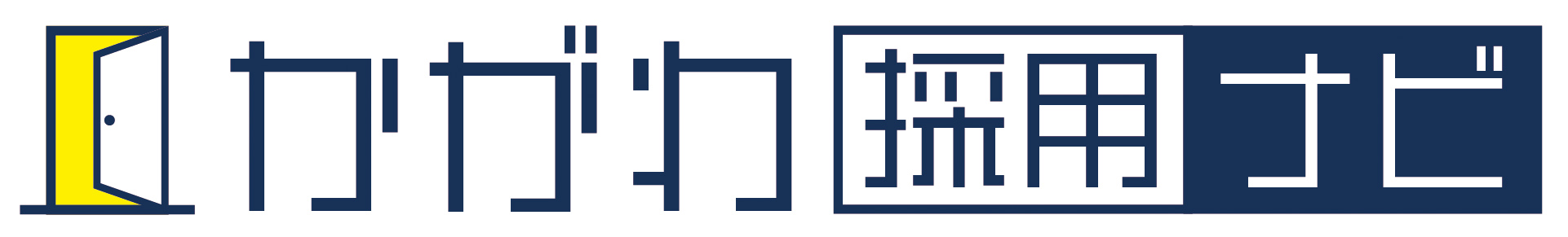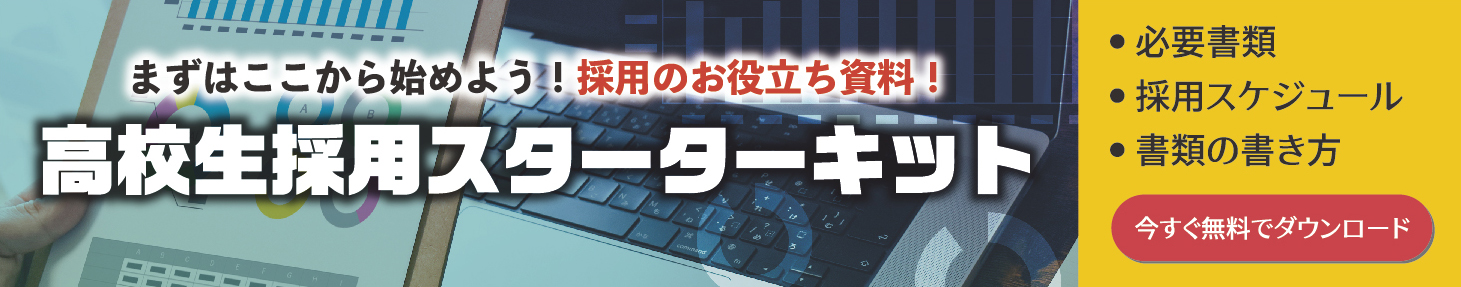5月病はなぜ起こる?離職を防ぐために会社が取るべき対策は?
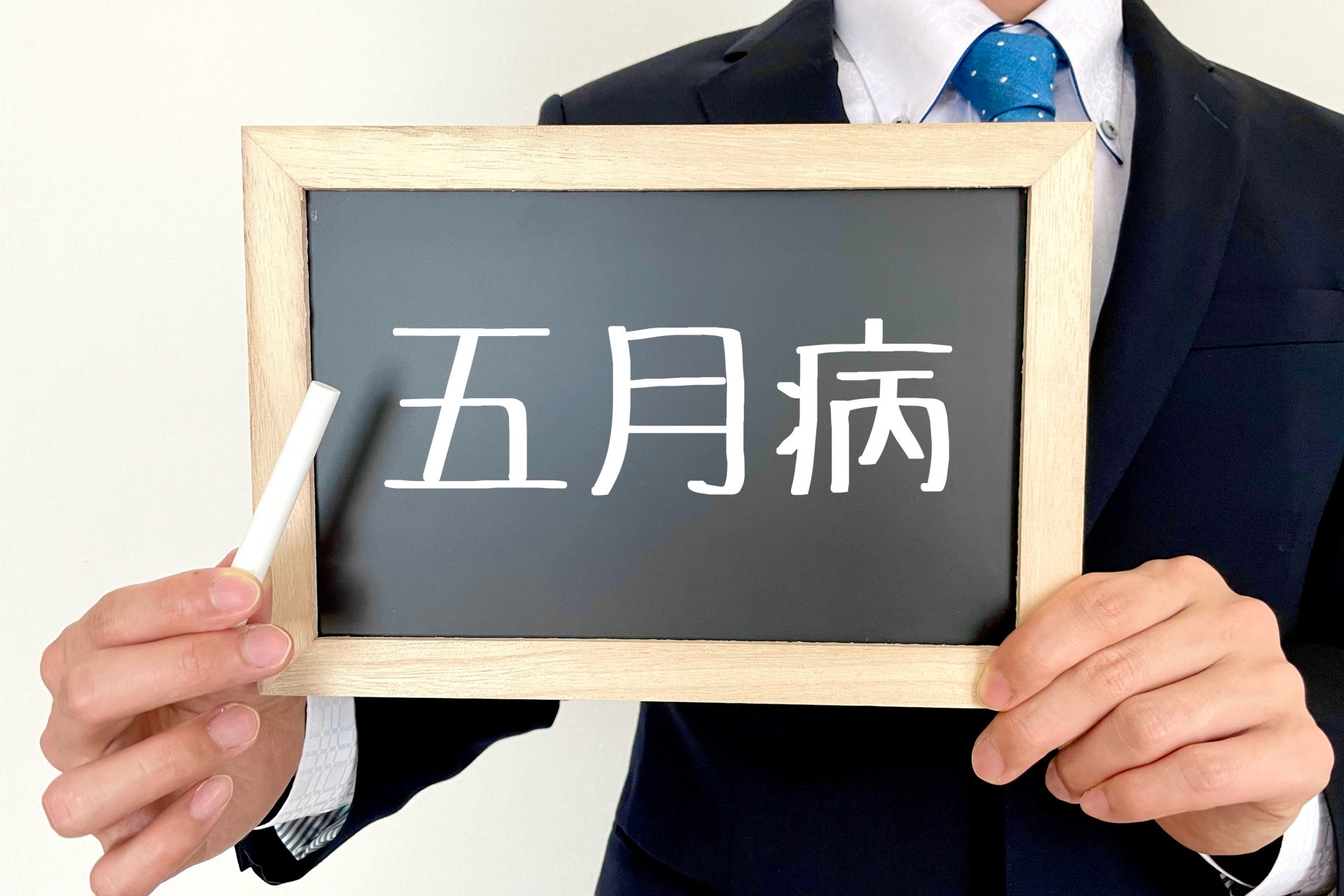
「5月病」という現象は、新しい環境に飛び込んだばかりの新入社員が、入社の興奮が落ち着き、日常の業務に追われる中で感じる疲れやストレス、モチベーションの低下を指します。この時期は、新しい生活リズムや職場の人間関係、業務内容への適応による疲れがピークに達し、離職を考える人が増えることが知られています。本コラムでは、なぜこの「5月病」は起こり、会社はどのようにしてこれを防ぎ、若手社員をサポートすべきなのかを解説していきます。
1.5月病とは?
「5月病」は、新入社員が職場に馴染み始めた頃に起こる、モチベーションの低下や仕事への意欲喪失の状態を指します。これは、大学や学校という以前の生活と、完全に異なる新しい職場環境とのギャップ、期待と現実との違い、人間関係のストレス、未経験の業務への不安など、さまざまな要因によって引き起こされます。
2.なぜ5月病が起こるのか?
①現実とのギャップ
新入社員はしばしば、職場や仕事に対して理想的なイメージを持って入社しますが、実際の仕事の量、ペース、厳しさが予想外だった場合、ショックを受けることがあります。また、自分が直面する課題の解決策が見出せず、フラストレーションを感じることがあります。
②人間関係のストレス
新しい環境での人間関係は、誰にとっても一大事です。特に新入社員は、同僚や上司とのコミュニケーションに不安を感じることがよくあります。自分の意見をどの程度表現すべきか、どのように協力し、信頼関係を築くかなど、日々の対人関係がストレスの原因となることがあります。
③適応の難しさ
新入社員は、企業文化、使われる専門用語、業務プロセスなど、新しいすべてに迅速に適応する必要があります。これによるプレッシャーは、「5月病」の一因となり得ます。
④GWの影響
新卒の新入社員にとって、5月のゴールデンウィークは特に敏感な時期となることがあります。この時期、友人との近況報告の中で他社の働き方や企業文化について聞く機会が多くなります。他社が提供する優れた条件や、職場の楽しい話を耳にすると、自分が所属する会社と比較してしまいがちです。その結果、他社の良い点だけが強調され、自社の状況が悪く見えてしまうことがあるのです。このような比較による不満や不安が、5月病の原因の1つとなることがあります。
3.会社が取るべき対策
①メンター制度の導入
メンターは、新入社員にとっての信頼できる相談相手となり得ます。メンターが業務だけでなく、職場での人間関係やキャリア発展についてのアドバイスを提供することで、新入社員は自分が一人で問題を抱え込む必要がないと感じます。メンターとなる社員には、コーチング技術のトレーニングを受けさせ、効果的なアドバイスやフィードバックを提供できるよう支援することが重要です。
②定期的なフィードバック
定期的なフィードバックは、新入社員が仕事の進め方を適切に調整し、自己成長を感じることを助けます。また、フィードバックを通じて新入社員の不安や疑問を明らかにし、適切なサポートを提供できます。
③研修やワークショップの実施
新入社員のスキルアップやストレスマネジメント、コミュニケーション能力向上のための研修やワークショップを定期的に実施します。
④健康管理のサポート
精神的なストレスだけでなく、新しい環境での生活リズムの変化による身体的な不調にも対応するため、健康診断やカウンセリングの機会を提供します。
⑤オープンドアポリシーの推奨
どんな小さな悩みでも相談しやすい環境を作るため、上司やHRがオープンドアポリシーを徹底し、コミュニケーションの壁を取り除きます。
まとめ
「5月病」は、新入社員が職場への適応に苦労しているサインかもしれません。会社側が積極的にサポートし、彼らが安心して働ける環境を整えることが、離職を防ぎ、長期的な成長へとつながる鍵となります。もちろん新入社員だけでなく、ベテラン社員のフォローも心掛けてください。
なお、かがわ採用ナビでは、香川県内の企業の採用サポートを実施しています。「どのように採用活動をすればよいか分からない」「採用戦略をしっかり考えたい」など、些細なお悩みでも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。