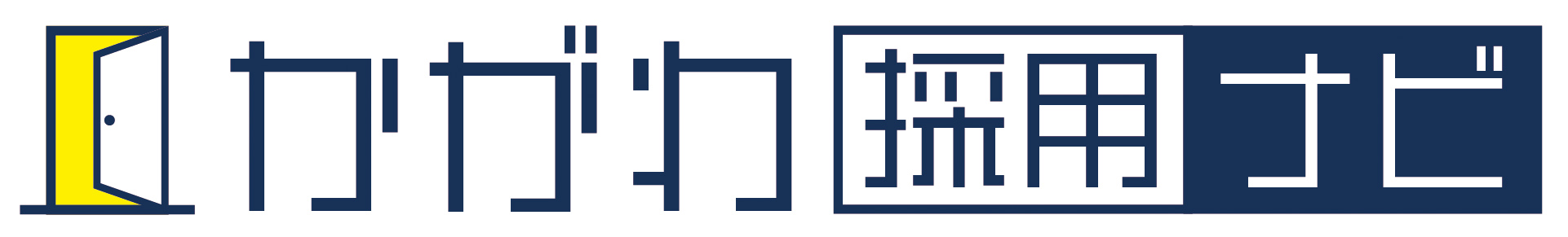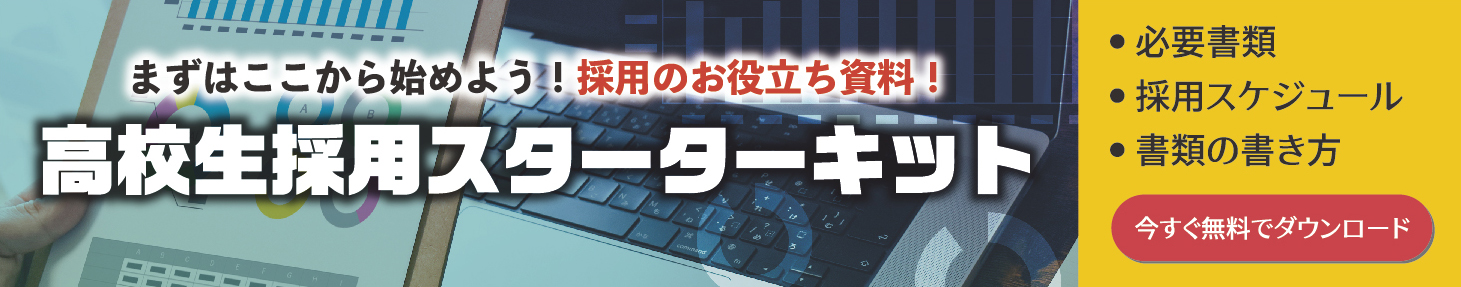採用担当者必見!若者の定着率を上げる方法!

近年、採用担当者の方は人材確保で一番頭を抱えているのではないでしょうか。やっと採用出来て、これから即戦力となって働いてもらおうとしている中で、辞職していく新入社員が多いということはこれからの企業存続していく上でも大きな問題となっていきます。そんな新入社員の定着率を上げていくためにどんな対策を行っていけば良いかを解説していきます。是非、採用担当者の方はご活用ください。
1.定着率の現状
新規学卒者の3年以内の離職率は3割といわれており、3年以内の社員定着率は7割となりますが、ここでは、離職率などの厚生労働省の統計資料から社員定着率の平均を見ていきます。
厚生労働省の調査によると、新規学卒就職者の就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者39.2%、新規大卒就職者32.0%と集計しており、入社3年目におよそ3割が離職、つまり入社3年目の社員定着率は7割であることが統計としても確認できています。
2.定着率が上がらない会社の特徴
仕事が自分に合わないため
このように回答したのは、就職1年未満~3年未満の社員が多く、女性より男性の方が理由として挙げる割合が高いです。仕事内容というのは、就職前に説明されていたとしても実際にやってみないと自分に向いているか分からないのです。
そのため、実際にやってみたら自分には向いていなくて、毎日の仕事が苦痛で耐えられず辞めてしまう人が多いです。
労働時間・休日・休暇の条件が良くなかったため
こちらは、1年未満から3年以上の社員まで多くの社員が挙げた理由になります。
1年~3年未満は上記の理由と変わらず、入ってみたら労働時間が長かった・休日出勤があったなど、入社後のマイナスなギャップが原因です。
3年以上でこの理由を挙げている人は、子育てや介護などライフスタイルの変化により生じた不満を感じている人でしょう。
時短勤務がなかったり、マタニティハラスメントなどで会社に居づらくなってしまうなどが原因です。
人間関係が良くなかったため
こちらも1年未満~3年未満の社員の多くが理由として挙げています。
また、人間関係を理由に挙げているのは女性が圧倒的に多く、3年以上勤めている女性も上から3番目の理由として挙げています。人間関係に悩むのは、男性より女性の方が多いようです。
やはり、ほぼ毎日顔を合わせる人と上手くやれないというのはストレスです。それが耐えられず、やめてしまう人が多いようです。
賃金の条件が良くない
賃金への不満は、若手より3年以上の社員の方が不満を抱えているようです。
また、女性よりも男性の方が賃金を重視するようです。こちらもやはりライフスタイルの変化で家庭を支えなければいけないためお金がもっと必要になるためでしょう。
または、昇給が遅かったり給料がなかなか上がらないなどの理由もあると考えられます。
結婚、子育てのため
こちらの理由は3年以上働いている女性に多い離職理由です。
夫の転勤先についていく、子育てのために離職せざるを得ない場合が多いと思われます。
最近は働き方改革によりテレワークを推奨している会社も増えてきているとはいえ、まだまだ理解のある会社は少ないです。
そのため、ライフスタイルの変化で離職を余儀なくされる社員も多いのではないでしょうか。
会社に将来性がないため
こちらは3年以上勤めている男性が多く、上から3番目の離職理由に挙げられています。
世の中の変化に伴い、これまで安定していた職業が今では必要なくなってきているというような状況はいろいろな業界で起こっています。
そのような変化を鑑みて、「会社、仕事がなくなるのではないか」という不安に駆られ、離職に至る社員が多いのではないでしょうか。
3.定着率青王に向けた施策
社員が離職する理由は、若手は入社後のギャップ、ベテランは周囲の様々な変化が関係していることが分かっています。社員が定着するためには、会社に対する満足度を上げることが大切です。 満足度に関する実例として、株式会社LIXILさんが社内で行ったwebサービスによるアンケート「従業員満足度調査サービス」を実施した結果から、満足度に高い影響が出ている設問が5つあったようです。その重要度の高い設問とは、以下のものです。
①経営陣は社員の声に耳を傾けている
②適切な目標・目的を設定し、共有してくれている
③公正に評価し報酬に反映させている
④社員を最も大切な財産として扱っている
⑤部下の仕事ぶりを正当に評価してくれています
コチラを見ると、給料や福利厚生よりも、コミュニケーションや上司からの正当な評価が社員の満足度を上げていることが分かります。
つまり、従業員の満足度を高めるためには、
- 時間や給料を上げるよりもまず、承認欲求を満たすこと
- 社員の行動、言動を見て、聞いて、評価してあげること。
- 給料やボーナスはただ上げるのではなく、上がった理由を伝えてあげること
この3つが重要です。
時間や給料を上げるよりもまず、承認欲求を満たすこと
離職理由で上位に挙がっているため、時間や給料に対する不満を無視することは出来ません。 しかし、社内で自分が「期待されている、評価されている」と感じたら誰でも嬉しいですし、仕事での承認欲求が満たされモチベーションにも繋がります。
社員の行動/言動を見て聞いて、評価してあげること
そして、承認欲求を満たした後はその評価を給料や待遇に反映させます。
そうすることで、給料に対する不満は解消できます。
自分が頑張れば頑張るだけちゃんと評価してもらえると分かれば、上司や経営者に対する信頼度も高くなっていきます。
給料やボーナスはただ上げるのではなく、上がった理由を伝えてあげること
評価し、給料を上げることでモチベーションは上がります。
しかし、自分のどの頑張りが評価されたのか、上司や経営者から伝えられた後で昇給するのとそれがない場合ではモチベーションの上がり方も変わっていきます。
特に、若手社員は上司や社長に見てもらいたい、認められたいという欲求が高いです。若手は初め、やる気があり何事にも一生懸命です。
そのモチベーションを維持させるために、上司や社長は若手の働きをしっかり見守り、「【何をした】から良かったよ!」と具体的な理由を述べて褒めるように努めましょう。
いくら評価してもらえると言っても、長時間労働や休日出勤などを行っていたらどんな社員でも体を壊してしまい、結果的に離職に繋がってしまう可能性が高いです。
それを防ぐためにも、法定労働時間を守り、週休2日制を遵守しましょう。
これで解決!会社が今すぐやるべき制度
従業員の満足度を高めるために重要なことが分かったところで、導入すべき制度をお伝え!これらの制度を導入することでさらに従業員を理解し、満足度を高めることが出きます。
1on1ミーティング
定期的に上司と部下1対1のミーティングを行います。
これは、2人の話というよりも上司が部下の状況や心境を知るために行われるものなので、部下が主体で話をするようにします。普段はなかなか言えない不満や不安・人間関係・仕事やキャリアに対する疑問など、上司と部下が気持ちや考えを共有することですれ違いを無くし、部下の上司に対する不満を無くす作用もあります。
そのため、部下がリラックスしながら素直に自分の気持ちを話せる場所・空間で行うことが大切です。
(例:2人でゆっくり話せる個室で防音の部屋、飲み物を飲みながら、横並びで話をするなど)
教育研修
新卒や未経験者に対して教育を行うのはもちろんのこと、ベテラン社員のスキルアップのための研修を受講できるような環境を整えることも大事です。
新卒や未経験者はモチベーションが下がらないように基礎から応用まで研修を行い、自分に自信をつけてもらいます。
ベテラン社員は、今あるモチベーションを保ち続けるためにスキルアップ研修を受けられる体制を整えます。
働き方改革ワークショップ
社内で現状の課題を出し合い、解決するためにはどうしたらいいか話し合います。
何グループかに分かれて解決策を発表し、一番実現性があると思った解決策を、課題と共に社長に発表します。社長は、社員が出した課題を重要視し、出来る限り解決策を前向きに考えるようにします。または、別の方法で課題を解決する方法を考えます。というのも、折角課題を指摘して解決策まで考えたのに何も変わらなかったら、会社に対する不信感や不満が増えるだけです。また、会社の課題を社員全員で考え解決しようとすることは、社員の親密度も上げる効果があります。
ポイント☝
解決策を採用したり、何か制度を導入したりする時は「従業員のために」という部分を強調するようにします。
また、従業員1人1人をしっかり見ていることを行動や言葉で伝えるようにしてください。
大事なのは、社員を理解しモチベーションをあげること
「従業員のため」と言いながら、自分の考えや方法を押し付けている上司や経営者では、全く意味がありません。
従業員の定着度が低くなっていく一方です。 従業員の満足度を上げ、定着率を上げるためには、心から従業員のことを考え、理解する姿勢を見せ、正当に評価し会社を変えていこうという前向きな姿勢がないといけないです。
「従業員のことを考える」と言葉で言うのは簡単ですが、数多くいる様々な考えを持った人間を全員満足させるのは至難の業です。
少しでも満足度の高い従業員を増やすために、理解したいという姿勢を見せることが大切です。
4.まとめ
従業員の満足度を高めるのは、一朝一夕では難しいということが分かったではないでしょうか。会社は多くの社員が動くことで成り立っているので、会社経営の手助けをしてくれている従業員が少しでも満足できるような会社を作るために、従業員の声に耳を傾けることが大事です。
多くの従業員が欲しいと思っている制度を導入するだけで離職率がかなり減り、さらには就職希望者が増える可能性も高いです。変化を怖がるのではなく、変化によって得られるものに目を向けてみることも重要です。